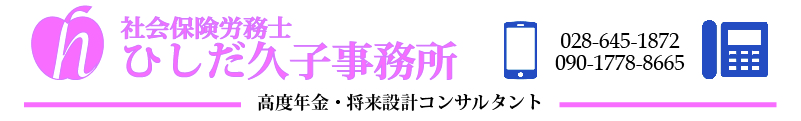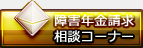TOPICS
第3号被保険者について
今更ですが、さきごろ新聞をちょっとにぎわした国民年金の第3号被保険者についてです。
イメージしやすいように夫が外で働き、妻は専業主婦という設定ですが、逆パターンも同じです。
昭和61年3月までは、サラリーマンの妻は国民年金は任意加入でよい、という制度でした。
しかし、それでは、任意加入しなかったサラリーマンの奥さんは65歳になったときに無年金者になってしまいます。
そこで、昭和61年4月からは、そうしたサラリーマンの妻たちを対象に、届けることで保険料は個人で納付しなくてもすむ国民年金第3号被保険者という制度ができました。
ただし、当時は、対象となる人は自分で市役所等に出向き手続きをしなければなりませんでした。
しかも、届出をしたときから2年間しかさかのぼれなかったのです。
サラリーマンの妻にとってはこんなにいい制度なのに当初あまり広く知れわたらなかったためか、その後改正が行われ、自分で届出せずとも夫の会社を通して3号の手続きができるようになりました。
また、2年より遡る分についても特例の届けというものができるようになり、今は、条件にあう人であれば、届ければ昭和61年4月までさかのぼって3号になれます。
これであれば、年金受給の資格である最低25年の被保険者期間を満たすことにもかなり有利にはたらきます。
ただ、ここにはやはり落とし穴があるのです。
夫が転職する場合、妻は夫がサラリーマンではなくなるのですから、3号ではなくなります。
この時、自分で市役所等に行って、3号から国民年金の強制加入者である1号への種別変更という手続きをしなくてはなりません。
そして、夫があらたに就職したらまた会社を通して3号になれます。
夫が転職を繰り返している場合など、そのどこかの部分でこの手続きが抜けていると、ずーっと3号のままになっていたりします。
そして、自分が年金をもらう時に改めて3号→1号→3号→1号→3号といった手続きをすることになり、面倒な上、当然1号の時の保険料は納付していませんから、年金額が少なくなる・・・ということになります。
年金額が少なくなっても老齢年金は特例によりあとからでも訂正できるので、年金受給にさほど深刻な影響を及ぼすことはまれですが、障害年金となると大変です。
障害年金の初診日(その障害に起因する疾病ではじめて医師の診療を受けた日)が万一特例の届けで訂正すべきところにあった場合、届け出日より前は未加入とされますので障害年金がうけられなくなります。
基本的に障害年金は、初診日に年金制度に未加入では請求できないのです。
社会保険庁から届く年金定期便で自分が国民年金にはいっているからと安心しないで、ご主人に転職があった方はご主人との記録をつきあわせてください。