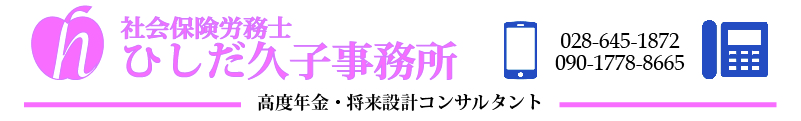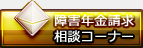TOPICS
失踪宣告と死亡一時金
失踪宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日としており、死亡一時金については失踪手続きが遅くなると審判の確定が出た時点で9年過ぎているような場合、給付を受ける権利が時効(2年)にかかるため受給できなくなることがおきていた。
死亡一時金は掛け捨て防止の考えを踏まえているはずなのに不合理と思っていたところ、このたび、死亡一時金の請求に関しては失踪宣告の確定日の翌日から2年以内の請求であれば支給されることとなった。今回、上記の例があり、年金事務所の窓口で、また、社労士として関わった案件でこんなことがありました、というお話をいくつかさせていただきたいと思います。
気を付けなければならないことなど、具体的なので参考にしていただければと思います。1.夫になる予定の男性が不慮の事故で死亡し、内縁の妻に遺族年金が支給された事案(生計維持関係の証明)
男性は日本人で請求者は外国人女性、入籍はしていません。
男性が死亡した前後請求者は日本にはいなかったこと、また日本滞在時においても同居していなかったことなどから、遺族年金の請求ができるかどうか微妙な案件となりました。
内縁の妻でも遺族年金は請求できますので、生計維持関係の証明ができるか否かにかかってきます。
そこで生計維持の証拠として何を提出したかですが、まず、日本における女性のアパートの家賃を男性が支払っていたことの証明と手紙と通話の記録です。これによりほぼふたりが内縁関係にあるという事実がわかってもらえました。しかしそれだけでは決定とはならず、実地調査が行われました。調査の結果、男性宅が新居として女性を迎える準備を整えていることなどから遺族年金は支給されることが決定しました。2.未支給年金請求と遺族年金請求が別々にされた事案
男性が死亡しました。この方は再婚していて先妻の子がいます。再婚した妻は他県に住所があります。しかし、どういう事情か亡くなる数年前には先妻の子の住まいの近くの施設に入所し最期を迎えました。当然、入所中の面倒や細かい出費なども先妻の子の負担となり、未支給年金(死亡者が受ける権利のある年金でまだ支払われていない分)の請求権はこちらにあります。さらに、過去の厚生年金記録が追加となったため数百万円が未支給分として支払いがされることになりました。書類を整えてもらい未支給請求の受付をしました。
ところが、機構本部からこの方の未支給年金と遺族年金の請求がすでに他県で妻からされているというのです。
遺族年金は妻が受け取り、未支給分は子が受け取るということはできません。受給権の順位から、先妻の子の請求は取り下げていただいたのですが、気持ち的に不消化の案件でした。3.返納についてⅠ
受け取れない年金を何年何十年も受給し続けていたために起きた事案です。
遺族年金を受給中の女性が65歳になって老齢年金の請求に年金事務所の窓口までこられました。
年金請求の時には加給金の関係から配偶者の情報を確認します。
すると、この方再婚していらして配偶者がいらっしゃることが判明しました。
再婚されてから数十年たっているということです。
遺族年金は結婚すると失権します。
つまり、この方の場合すでに受け取れない年金をずっと受けていたわけで・・・。
直近5年分の遺族年金を返納しなければならなくなりました。4.返納についてⅡ
この返納についてはつらい思いをしました。
息子が死亡し、母親が死亡の手続きをされました。
子の死亡手続を親がしなくてはならない事実、これだけでも心は痛みます。
息子の年金には配偶者加給金がついています。
遺族年金の請求が妻ならできるのだが、と申し上げました。
すると、嫁は数年前に家出し連絡先もわからないため、実際はこの母親と息子の二人暮らしとのことです。
さぁ大変、このかなりお年を召していらっしゃるお母様に息子さんの年金についている配偶者加給金を返さなければならないことを説明しなければなりません。
泣かれました。私も泣きました。