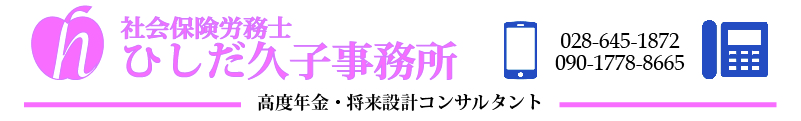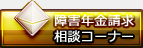TOPICS
被用者年金一元化で何が変わるの?
27 年 10 月以降、共済年金は厚生年金と名前を変えてそれぞれ別々だった制度を基本的に厚生年金に合わせる方向になります。
共済年金制度で大きく変わるのは
1. 職域加算がなくなります
2 . 60 歳前半に厚生年金加入の場合、支給停止ラインがかわります
3. 障害年金受給には保険料納付要件が必要になります
4. 障害年金を受けている場合、在職による停止がなくなります
5. 遺族年金の転給制度がなくなります
6. 遺族年金を受けることのできる障害のある子の要件が 20 歳未満となります現在の段階で色々ご質問を受けるなかで多いのは、上記についての心配がほとんどです。また、制度が動き出したら、現実にえっ、と思うような事が出てくるとは思いますが。
障害年金の仕事をしているせいか、 6 番のご質問は何回かいただきました。厚生年金制度では、遺族年金を受けることのできる障害のある子は 20 歳になるまでですが、現在、遺族共済年金は、障害がある子の場合、年齡の要件がないので 20 歳を過ぎても請求できています。それを厚生金年金制度のほうにあわせることになります。障害がある場合、現実的に就労は難しい事が多いので遺族年金が受けられると金額的に有利な場合もあるため、共済年金制度にあわせればよかったのに…
2 番の支給停止ラインですが、 60 歳前半は、基本的にお給料と年金を合わせて1ヶ月28 万円を超えると年金がカットされます。ただ、現在共済年金を受けていて厚生年金に加入されている方は1ヶ月 47 万円まで停止がかからないところ、いきなり 28 万円のラインにするのは厳しいということで、激変緩和措置というものが適用されます。計算方法は 3 種類あり、その中で一番少ない額が停止額となります。ただしこの措置の対象となる方は、一元化となる 27 年 10 月 1 日をまたいで在職されている方です。これから受給となる方は原則の 28 万円の支給停止ラインが適用されます。
1. お給料と年金の合計の1割が支給停止の上限
2. お給料と年金の合計の1カ月 35 万円までは保障
3. 原則通り 28 万円を超えた半分が支給停止
※お給料には前一年の賞与の 12 分の 1 が含まれます
※共済組合の職域加算は計算にいれない
※施行日前の支給停止月額を「調整前特例支給停止額」といい、1.2.の計算の時には調整前特例支給停止額を差し引いて計算し最後に加算するという方法をとりますたとえば、年金 12 万円 給料 50 万円の場合を想定してみましょう。
現在の停止額は
(12 + 50 ー 47) × 1/2=7.5
しかし 1 の場合そのまま計算すると
(12+50) × 1/10=6.2
となり、逆に有利になります。このように一元化前から停止がかかっていた場合は
(12+50-7.5) × 1/10=5.45
5.45+7.5=12.95
と計算します。結果全額停止になってしまうということです。
2 の計算でも 3 の計算でも全額停止なので、一元化後は年金が貰えなくなります。厚生年金を受けている昭和 12 年 4 月 1 日以前生まれの場合、在職老齢年金の支給停止対象外でしたが、一元化後は支給停止の対象となります。ただし、こちらの場合も厚生年金ですが、激変緩和措置が適用されます。現役の事業主の方でお給料が高い場合、注意が必要になります。
一元化で便利になるの原則「年金加入期間確認通知書」が不要になります。しかし、障害年金の請求は初診日のある機関に請求となるため、必用となる場合もあります。
基本、老齢年金、退職年金の請求先はすべての窓口で受け付け可能となります(年金機構でも共済組合でもワンストップで手続きができるようになります)
ご夫婦で年金をみると、条件によっては配偶者加給金、振替加算というものがついてくる場合があります。一元化前の条件は同じ被用者年金への加入が 20 年以上あるかないかですが、一元化後は共済年金も厚生年金となるため通算で 20 年以上あれば配偶者加給金がつきます。逆に、現在共済年金に 15 年、厚生年金に 15 年と、バラバラで加入期間を考える場合、振替加算がついた方が振替加算の対象とならなくなるということになります。
44 年の長期特例という制度がありますが、これは今まで通り共済期間、厚生年金加入期間と個々でみるので、合算はできません。
以上、10月からの動きだしに備えて知っておいていただきたい情報です。(端数処理計算や離婚分割、退職改定などまだまだたくさんありますがまた後日)